ヨーロッパの歴史ってとても長いですよね。いざ、勉強してみようと思うと、色々な国が登場して確かに流れが掴みにくいです。
この記事では、フランスの大学で西洋史・フランス史を専門に勉強している私が、西洋史の流れを簡単にわかりやすく説明します。
この記事はこんな方に向けて書いています。
- 西洋史の勉強をする前に大まかな流れを掴みたい。
- 教養としてさらっと西洋史を学びたい。
- 西洋史の本を読む前に、簡単に流れを知りたい。
- ヨーロッパに旅行に行く前に簡単に西洋史を学びたい。
それでは、さっそく古代時代から、ヨーロッパの歴史を辿りましょう。
古代ギリシア〜古代ローマ時代(~5世紀)
古代ギリシア時代
紀元前3000年頃、エーゲ海で文明が興ります。エーゲ海の島々で見つかったエーゲ文明は、クレタ文明やミケーネ文明とも呼ばれています。
この時期を起源とする物語が、現在まで語り継がれているイリアスやオデュッセイアですね。
やがて、ギリシアにたくさんの都市国家(ポリス)が誕生します。数あるポリスの中でも覇権を争ったのが、アテネとスパルタです。
約2000年にわたり人類史に大きな影響を与えた古代ギリシア文明。
政治分野では民主主義の発展、学問では哲学、文学、美術など、現代まで続くヨーロッパ社会の礎になっています。
ギリシア文明が繁栄を極めたのも束の間。ポリス間の対立により、古代ギリシア文明は滅亡していきます。
ヘレニズム時代
ギリシア地方の隣にあるマケドニアが力をつけていきます。
この時代の英雄がアレクサンドロス大王。ナポレオンも憧れた英雄の中の英雄。
戦がとても強く、中東を支配し、アジアのインドの辺りまでを制覇します。
アレクサンドロス大王の有名な壁画が、イタリア・ポンペイ遺跡の邸宅に残っています。
アレクサンドロス大王は若くして急死してしまいます。そして、その頃に力をつけてくるのが、古代ローマです。
古代ローマ時代
紀元前8世紀頃に、イタリア半島に古代ローマ文明が誕生しました。
始めは王政だった古代ローマですが、貴族政治を中心にした共和政に移行します。
古代ローマ内では、貴族と平民の対立が激しくなりますが、一方では、この時期にイタリア半島の外にまで領土を広げてローマ帝国を築き始めます。
この頃に活躍したのが、カエサルやポンペイウスです。
その後、アウグストゥスが初代皇帝となり、ローマ帝国を発展させていきます。
五賢帝時代には、「パクス・ロマーナ」と呼ばれる長期的な平和を実現しました。
それでも、広大な領土を統治するのは大変で、コンスタンティヌス帝といった力を持つ皇帝が現れるものの、ローマ帝国は崩壊の道を辿ります。

中世ヨーロッパ(5~15世紀頃)
ゲルマン民族の移動
東方からフン人が侵入してきたため、西ローマ帝国のあったヨーロッパ一帯にゲルマン人が移動してきました。
混乱の中、西ローマ帝国は476年に滅亡します。そして、ヨーロッパではゲルマン人が部族ごとに小さい国を作りました。
フランク王国の発展
ゲルマン人による小国が乱立するなか、力をつけたのがフランク王国です。
最初の王朝をメロヴィング朝と言います。
最初の王様はクローヴィス。彼は当時少数派だったキリスト教アタナシウス派に改宗し、カトリック教会の後ろ盾を得ることで、力を拡大していきます。
ゲルマン人の多くは キリスト教アリウス派 を信仰していましたが、メロヴィング朝のクローヴィスは 臣従達を引き連れて大人数でアタナシウス派 に改宗しました。
次の王朝がカロリング朝。重要な人物が8世紀に活躍するカール大帝です。
カール大帝は戦が強く、西ヨーロッパに領土を拡大します。現在のフランス・ドイツ・イタリア一帯を支配しました。
西暦800年にローマ教皇は、カール大帝にローマ皇帝の帝冠を授けました。この出来事をカールの戴冠 といいます。カール大帝をローマ皇帝と認めたことで、ローマ帝国が復活したことを意味します。
カール大帝亡き後は、強いリーダーシップを持つ君主が現れず、結局、広大な領土は3つに分裂しました。それが現在のフランス・ドイツ・イタリアの基となっています。
封建社会と荘園制度の発展
中世ヨーロッパの社会で覚えておきたいのは、封建制度と荘園制度の発展です。
封建制度とは、有力者が主君となり、臣下に土地を与えます。その代わりに臣下は主君に忠誠を誓い、軍事面で協力するシステムのことです。
この封建制度によって、皇帝・諸侯・騎士はそれぞれ自分の領土(荘園)を持ちました。各荘園には領主に対して納税や労働の義務を負う農民がいました。彼らのことを「農奴」と言います。
キリスト教世界の発展
もう一つ抑えておきたい中世ヨーロッパの特徴といえば、ローマ・カトリック教会が絶大な権力を持っていたことです。
西ヨーロッパに勢力を拡大したフランク王国を始め、神聖ローマ帝国・フランス王国・イギリス王国・イタリアの都市国家はローマ・カトリック教会と強い関係を持っていました。
キリスト教の聖地エルサレムをイスラム教から奪い返すために、ローマ教皇が中心となり、11世紀には十字軍が結成されました。
封建制度の崩壊と教会権力の低下
フランス王国とイギリス王国による百年戦争、十字軍による聖地エルサレム奪回の失敗、14世紀のペストの流行など、中世ヨーロッパの後半には封建制度の崩壊や教会権力が失墜する出来事が重なりました。
商業の発展による貨幣の浸透、百年戦争による諸侯の戦死、14世紀のペストの流行による人口の減少。これらの要因は封建制度や荘園制度を崩壊させました。
また、十字軍による聖地エルサレム奪回の失敗、14世紀のペストを止められないローマ・カトリック教会は、権力が低下していきました。
中世ヨーロッパ後半の危機により、ヨーロッパは近代へと移り変わっていきます。
近世ヨーロッパ(14~18世紀)
ヨーロッパの近世は、ルネサンス時代や大航海時代から始まり、フランス・イギリスを始めとした西ヨーロッパの王国で王権が強くなり、絶対王政が確立する時期にあたります。
ルネサンス
「ルネサンス」とはフランス語で「再生」を意味します。 中世は宗教中心の世界観でしたが、ルネサンス時代には人間や自然を重視する新しい考え方が広がりました。
中世に忘れ去られてしまっていた、古代ギリシャ・古代ローマの文化に再び焦点を当てて、イタリアを中心に芸術・学問・思想が大きく発展しました。
ルネサンス時代は、ヨーロッパが中世から近代へ進む大きな転換点となりました。芸術・学問・思想の新たな発展が、宗教改革や科学革命といった近代に繋がっていきます。
大航海時代
スペイン・ポルトガルが筆頭となり、ヨーロッパ諸国(主にフランス・イギリス・オランダ)がアメリカ・アジア・アフリカへ進出しました。
新大陸から金や銀がヨーロッパに流入し、経済が大きく変化します。貿易や植民地経営といった植民地進出によって、ヨーロッパは世界の中心へと成長していきました。
また、新大陸から農作物(トマト・ジャガイモ・トウモロコシなど)がヨーロッパに輸入されたのもこの時代。現在のヨーロッパの食文化にも繋がっていきます。
宗教戦争
ドイツの修道士 マルティン・ルター がカトリック教会に異議を唱えたことを発端に宗教改革が始まりました。
中世には強大な権力を誇ったカトリック教会ですが、この権威はさらに失墜します。
西ヨーロッパを中心にプロテスタントが誕生します。ヨーロッパはカトリックとプロテスタントに分裂し、フランスやドイツでは宗教戦争が勃発し内戦状態が続きました。
絶対王政
近世の時代の後半になると、国王が強大な権力を持つ「絶対王政」が確立しました。
その最たる例が、フランスのルイ14世。パリ郊外に豪華絢爛なヴェルサイユ宮殿を築き、華やかな宮廷文化が広まりました。
また、国王は軍隊や役人を支配し、国家の仕組みを強化していきました。
啓蒙時代から革命まで
18世紀になると啓蒙思想が広まります。ヴォルテール、ルソー、モンテスキューなどの思想家が自由や平等といった新しい思想を広めていきました。
このような社会情勢の中、イギリスでは革命が起こり、議会制度が整っていきました。フランスではフランス革命が勃発し、近代社会が幕開けします。
近代ヨーロッパ(18世紀末〜19世紀)
ヨーロッパ近代は、フランス革命(1789年) を大きな転換点として始まりました。これまでは生まれた身分が、その人の人生を左右するものでした。しかし、庶民が「自由・平等・国民の権利」を掲げて立ち上がり、社会や政治の仕組みが大きく変わっていきます。
フランス革命とナポレオン(1789〜1815年)
1789年、フランス革命 が勃発。王政が廃止され、共和国になります。そして、国民による政治が始まりました。 その混乱期に現れたのが ナポレオンです。一時期はヨーロッパの大部分を支配しましたが、1815年に失脚しました。
フランス革命後に広まった 「自由・平等・博愛」という理念は、その後のヨーロッパに大きな影響を与えました。
産業革命と社会の変化(18世紀後半〜19世紀)
イギリスで始まった 産業革命 により、ヨーロッパにも蒸気機関や工場生産が広がります。都市に労働者が集まり、資本主義社会が形成されました。 鉄道や蒸気船で人や物の移動が加速。世界が一気に近くなりました。
国民国家の形成と自由主義(19世紀)
産業と革命の影響で、「国民国家」の考え方が広がりました。 1848年には「ヨーロッパの春」と呼ばれる革命の波が各地に広がり、自由や民主主義を求める動きが活発化。 19世紀後半には、イタリア統一(1861年)、ドイツ統一(1871年) が達成されました。
帝国主義と植民地拡大(19世紀後半)
工業化が進むと、資源と市場を求めてヨーロッパ列強は世界に進出。 イギリスは「世界の工場」となり、アフリカやアジアを植民地化。 フランス、ドイツ、ベルギーなども加わり、ヨーロッパの各国では帝国主義が広がりました。
ヨーロッパ近代は、フランス革命から始まり、市民の自由と平等の理念が広がると共に、産業革命を起点として資本主義や帝国主義が広まりました。
ヨーロッパ現代史(20世紀〜現在)
ヨーロッパの現代史は、二つの世界大戦を経験し、分断と統合を繰り返してきた歴史です。戦争の悲劇を乗り越えて、今日の平和と統合へと進んできました。また、ヨーロッパの近代に芽生えた自由主義や資本主義により人々の格差が広まり、共産主義というような考え方が誕生します。この考え方の違いは、戦後の対立となる冷戦にも繋がっていきます。
第一次世界大戦(1914〜1918年)
きっかけはサラエボ事件(オーストリア皇太子暗殺)。 ヨーロッパ列強の対立がピークとなりヨーロッパ各国が参加する総力戦に。 連合国(イギリス・フランス・ロシア・アメリカなど)が勝利。 ドイツやオーストリアは敗北し、ヨーロッパ地図が大きく変わりました。
第二次世界大戦(1939〜1945年)
ドイツのヒトラー、イタリアのムッソリーニ、日本の軍国主義が台頭。 ナチス・ドイツがヨーロッパを席巻しましたが、連合国が勝利。 ヨーロッパは戦争で甚大な被害を受けました。この経験から「二度と戦争をしない」という強い決意が生まれます。
冷戦とヨーロッパの分断(1945〜1989年)
戦後、ヨーロッパは西側(アメリカ・西ヨーロッパ) と 東側(ソ連・東欧) に分断。 ベルリンの壁(1961〜1989年) は、その象徴でした。 西ヨーロッパでは経済協力が進み、徐々に「統合」への道が開かれました。
統合するヨーロッパ(1990年代〜)
1989年、ベルリンの壁が崩壊し、冷戦が終結。 1993年に ヨーロッパ連合(EU) が発足。 ユーロ通貨の導入(2002年)や東欧諸国の加盟で、ヨーロッパはかつてない統合を実現しました。
現在のヨーロッパ
経済危機(ギリシャ債務危機など)、イギリスの EU離脱(ブレグジット)、難民問題、ウクライナ戦争など、課題は山積しています。しかしヨーロッパは依然として「平和と協力の統合のモデル」として、世界に大きな影響を与えています。
ヨーロッパ現代史は、二度の世界大戦を経験し、冷戦による分断、統合と平和の模索を探ってきました。
過去の戦争を教訓に、「協力して平和をつくるヨーロッパ」という姿勢が、今のEUにつながっているのです。
まとめ
古代ギリシア時代から古代ローマ時代を経て、ヨーロッパの源流が出来上がりました。
約1000年続いた中世ヨーロッパでは、封建社会・キリスト教の世界が構築されました。
中世の価値観が大きく変わり、近世ではルネッサンス・大航海時代・宗教改革といった出来事が起こります。カトリック教会の権威が弱くなるにつれて、その代わりに王権が強くなり、絶対王政の王国が誕生していきます。
近代には市民革命・自由主義・資本主義を発端として、現代にまで繋がる社会制度を構築しました。二つの世界大戦や冷戦を経験し、ヨーロッパは統合と平和という価値観を大切にしています。
ヨーロッパの歴史について、もっと詳しく学んでみたいと思った方は、おすすめの本も読んでみてください。


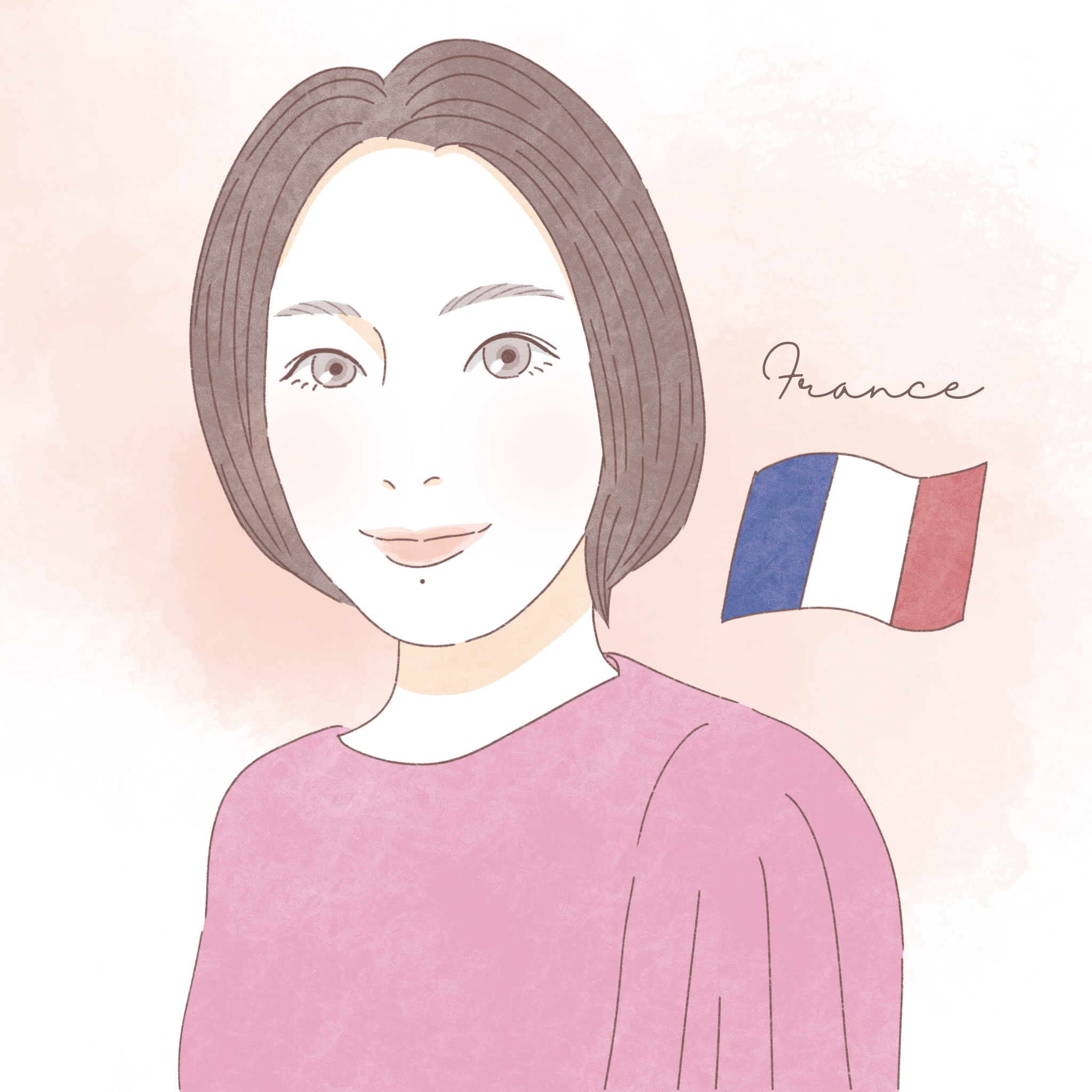

コメント